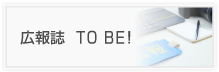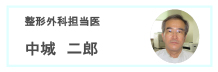名誉院長の麻生だより
明治43年8月1日、43歳の夏、夏目漱石は、胃潰瘍が悪化し、8月24日には多量の吐血があり30分ほど意識を失い、死の淵をさまよっていたといいます。激しい吐血は奥さんの衣服を血で汚すほどで、医師2人が脈を取りながら、「これはだめですね」「お子さん達を呼んだ方がいいですね」とすら言うほどの危篤状態でした。
この時の入院生活について、漱石の「思い出すことなど」に詳細に記されています。その中に
「医師は職業である。看護婦も職業である。礼も取れば、報酬も受ける。ただで世話をしていない事はもちろんである。彼等をもって、単に金銭を得るが故に、その義務に忠実なるのみと解釈すれば、まことに器械的で、実も蓋(ふた)もない話である。けれども彼等の義務の中(うち)に、半分の好意を溶き込んで、それを病人の眼から透かして見たら、彼等の所作(しょさ)がどれほど尊くなるか分らない。病人は彼等のもたらす一点の好意によって、急に生きて来るからである。余は当時そう解釈してひとりで嬉しかった。そう解釈された医師や看護師も嬉しかろうと思う」という記載があります。
「作業と仕事は違う」ということを、私は言い続けて参りました。散髪屋さんが、「私の仕事は髪を切ることです」と言った時、それは違います。髪を切ることは作業に過ぎません。髪を切ってあげて、お客さんが喜んだとき、初めて仕事となります。
夏目漱石の記載にある「義務に忠実なるのみ」という働きは作業、漱石が嬉しかった「義務の中に半分の好意を溶き込んだ所作」が仕事ということになります。
私たちの仕事が、患者さんの目から見て、尊く見えたり、嬉しかったりするのは、「好意」があるからなのでしょう。
ナースコールを押せば、その病院の質がわかると言われます。呼ばれたらすぐに対応しましょう。「どうされましたか?」と言われても、何をどう説明していいのかわからない時があります。すぐに病室に行ってあげましょう。その時必ず持っていかなければならないものは、笑顔であり、その患者さんに対する思い、その人を理解しようとする感性です。これが「好意」の基本だと思います。
令和元年5月24日